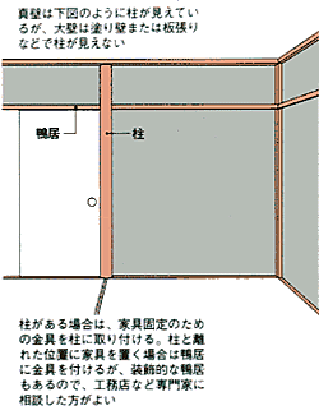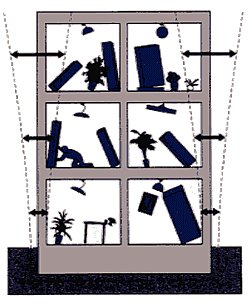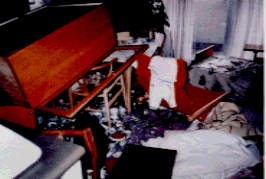地震による家具の転倒を防ぐ災害対策(2)「壁ならどこにでも固定できるってわけじゃないよ」
災害対策:家具の固定方法1
「壁ならどこにでも固定できるってわけじゃないよ」
災害対策:家具の固定方法1
さて、地震で揺れても家具が倒れないよう正しく固定するには、どうすれば良いのでしょうか。
それには、家具が地震の揺れに対して建物と一体的に動くように柱や鴨居、壁などに固定することが大切です。
しかし、最近では、昔からの日本家屋のようにしっかりした木の柱や鴨居のある家は少なくなってきたので、壁への固定が最も一般的な家具の固定方法といえます。
見かけは同じでも、実は違う壁の内側
ひと口に壁と言ってもいろいろな種類があります。
たとえば、木造の戸建住宅には真壁、大壁、2×4(ツーバイフォー)の壁が多く用いられています。
また、集合住宅などにはコンクリート壁や断熱材の入った防露壁などが用いられています。
そして、木造の戸建住宅でも集合住宅でも、木造軸組壁と呼ばれる木の桟のある間仕切りのための壁が使われています。
こうした壁には、家具を固定できる壁と、固定してはいけない壁があるので注意しましょう。
肝心なのは壁の中の桟を探すこと
家具を壁に固定するには、まず、壁のなかに隠れている桟を探し出す必要があります。
桟には、縦方向の縦桟と横方向の横桟がありますが、縦桟を見つけられれば、家具の高さにかかわらず、壁に固定することができます。
この縦桟の位置を確実に知るには、やはり設計図を手に入れるか、施工会社に問い合わせることです。
しかし、そういう手立てがない場合は、ドライバーなどの太い柄の部分で、壁を2cmずつ横にずらしながら叩いてみましょう。
桟は、30cmあるいは45cmに1本の間隔で入っているケースが多いようで、桟の入っている部分と空洞の部分では、音や感触に微妙な違いが感じられます。
叩いてみて固いコンコンという音がしたら、そこには桟が入っていると考えてよいでしょう。
桟が入っていない部分は、叩くと太鼓状に響く音がします。
ここに固定のための金具を取り付けても、効果は期待できません。
なお、ホームセンターやDIYショップでは、壁の桟を見つけるためのセンサーやプッシュピンが市販されています。これらを活用すると、より正確に桟を見つけることができます。
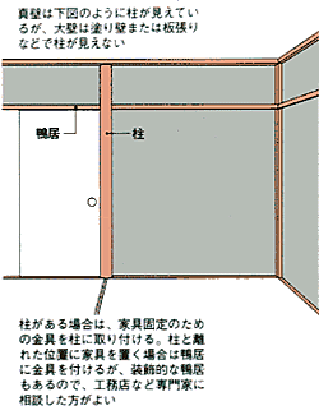
縦桟の探し方
家具を固定できない壁もある
ところで、最近の集合住宅に使われるS1壁やGL壁といった防露壁には桟が入っていないので、壁に直接、家具を固定することはできません。
そのうえ、コンクリートに発泡スチロール系の断熱材を 接着しているため、もしも家具を固定した場合、地震で揺れると家具の重さで壁の表面がはがれてしまう危険性があります。
一般的に防露壁の使用範囲は限られていますが、特にS1壁の場合、叩いた時の音や感触がコンクリート壁と間違えやすいので注意が必要です。
壁の種類がわからないときは専門家に相談を
多くの集合住宅の戸境壁はコンクリートでできていますが、なかには軽量鉄骨を桟とし、両側にボードを貼った乾式戸境壁を使うことがあります。この壁は、遮音や耐火の問題上、穴をあけることはできません。
このように、壁には種類が多く判別が難しいので、不明な点がある場合は、必ず工務店などの専門家に相談しましょう。
そのうえ、集合住宅の場合、賃貸住宅はもとより分譲住宅でも、隣戸との境の壁や外部に面する壁は、一般的に共用部分とされています。勝手にコンクリート壁に金具などを取り付けることはできない場合があるので、管理事務所や管理組合に確認をする必要があります。
災害対策:家具転倒のメカニズムを知る
「へえ。家具って、こんなふうに倒れるの」
重心が低ければ安定するはずだが...
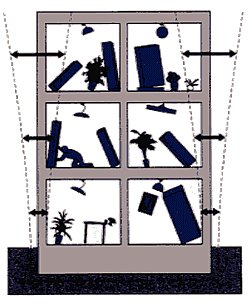
一般に家具であれ、建物であれ、ものにはすべて重心があり、それぞれの重心の位置は、プロポーションつまり幅や奥行き、高さ、そして重量などによって決まります。
この重心が、低ければ低いほど倒れにくいはずですが、造り付けでない家具のように床の上に置いただけのものは、重心の低い物であっても、実際には建物の構造や階数、置かれた部屋の状況によって倒れやすさが違ってきます。
たとえば、建物が鉄筋コンクリート造の集合住宅であるか、それとも木造の戸建住宅であるかなどによって揺れ方は違いますし、同じ集合住宅でも、建物の高さや階数によっても、揺れ方は違います。
家具は形や置かれた条件で多様な動き方をする
こうした建物本体の揺れ方、家具それぞれの揺れ方、あるいは家具を置いた床材の種類などによって、家具は様々な動き方をするわけです。
具体的には、洋ダンスや冷蔵庫のような背の高い家 具や家電製品には、前後に揺れながら歩いて移動してしまうロッキング移動と呼ばれる動きもみられます。
また、食器棚や整理ダンスのように積み重ねてある家具の上の部分や、テレビ台に載っ たテレビなどがジャンプをしたり落下するケース、あるいはロッキングを起こさずに床面を滑って移動をするケースなど、置かれた条件によってその動きは多様です。
家具を転倒させないためには固定が必要
地震で大きく揺れても、家具が動かないようにするには、大きな力が必要です。
たとえば、家具の上部で支えるケースでは、家具の全重量の1/2以上の力が必要となります。
いずれにしても、地震の揺れによる家具の転倒や移動を防ぐためには、できるだけ建物本体に、家具をより安全に固定しておきたいものです。
「家具が倒れると逃げ道まで塞がれて恐いね」
出典「総務省消防庁」
阪神・淡路大震災に見る家具転倒の状況
平成7年1月17日午前5時46分、
兵庫県南部を襲った直下型地震は、マグニチュード7.3、震度7を記録、死者行方不明者は6千人を超えました。
また、負傷者は4万3千人を数え、そのなかには建物に特別な被害がないにもかかわらず、家具の転倒や散乱によって、逃げ遅れたり室内でケガを負った方も多数含まれています。
これは、室内に家具や電化製品などを多く置くようになった近年の住宅事情によると思われます。
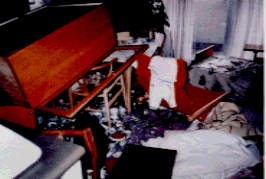
約6割の部屋で家具が転倒、散乱した
この阪神淡路大震災における震度7の地域では、住宅の全半壊をまぬがれたにもかかわらず、全体の約6割の部屋で家具が転倒し、部屋全体に散乱したというデータ(※1)があります。
しかも、ただ倒れるだけでなく、食器棚などは扉が開いて中の食器類が散乱し、また、冷蔵庫やピアノは移動してしまいテレビや電子レンジが飛ぶといった、日常では考えられない現象も確認されています。
つまり建物が無事でも、家具が転倒するとその下敷きになってケガをしたり、室内が散乱状態のために延焼火災から避難が遅れてしまうなど、居住者被害も大きくなるというわけです。
※1 日本建築学会「阪神淡路大震災 住宅内部被害調査報告書」
内部被害による怪我の原因
震度5強でタンスが倒れることも
平成8年2月に気象庁が発表した震度階級関連解説表によると、「震度5強」で"タンスなど重い家具が倒れ、テレビが台から落ちることがある"と想定されています。
わが国では平成5年から7年ま
での三年間に、震度6以上の強い地震が数回あったうえ、震度4や5といった地震は珍しくありません。
室内での居住者被害を防ぎ、安全な避難経路を確保するためにも、家具を固定しておくことが重要です。
「壁の桟と家具の桟をL型金物でとめるのね」
「冷蔵庫やピアノもそのままでは危ないよ」
「家具の配置にも工夫が大切なのね」
「重い物は低い所へ−当り前のことも忘れずにね」
災害対策〜ご家庭での備え〜これだけ準備
トップページ